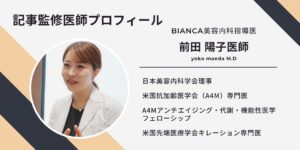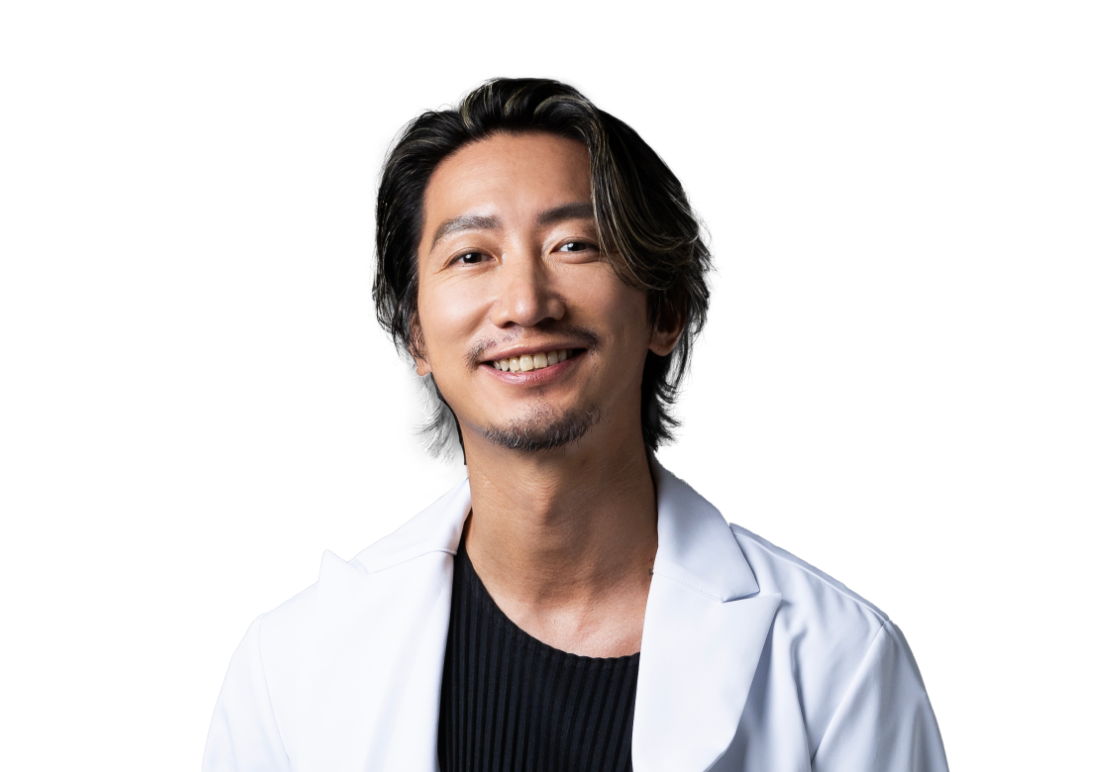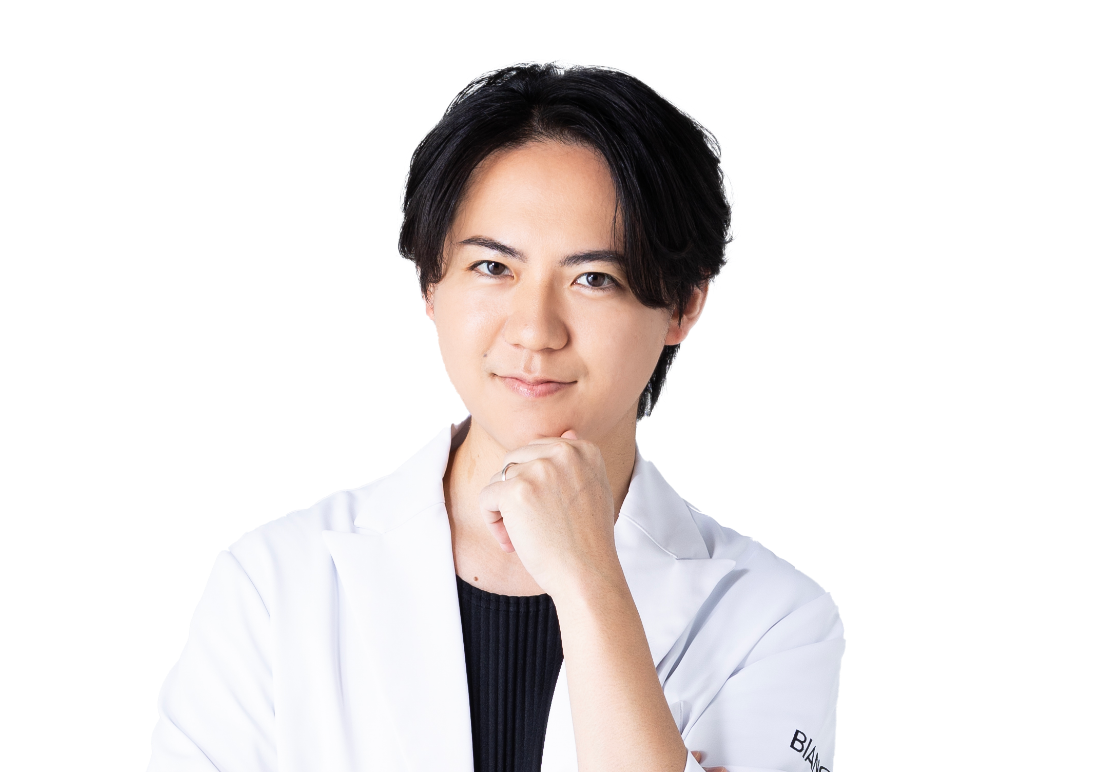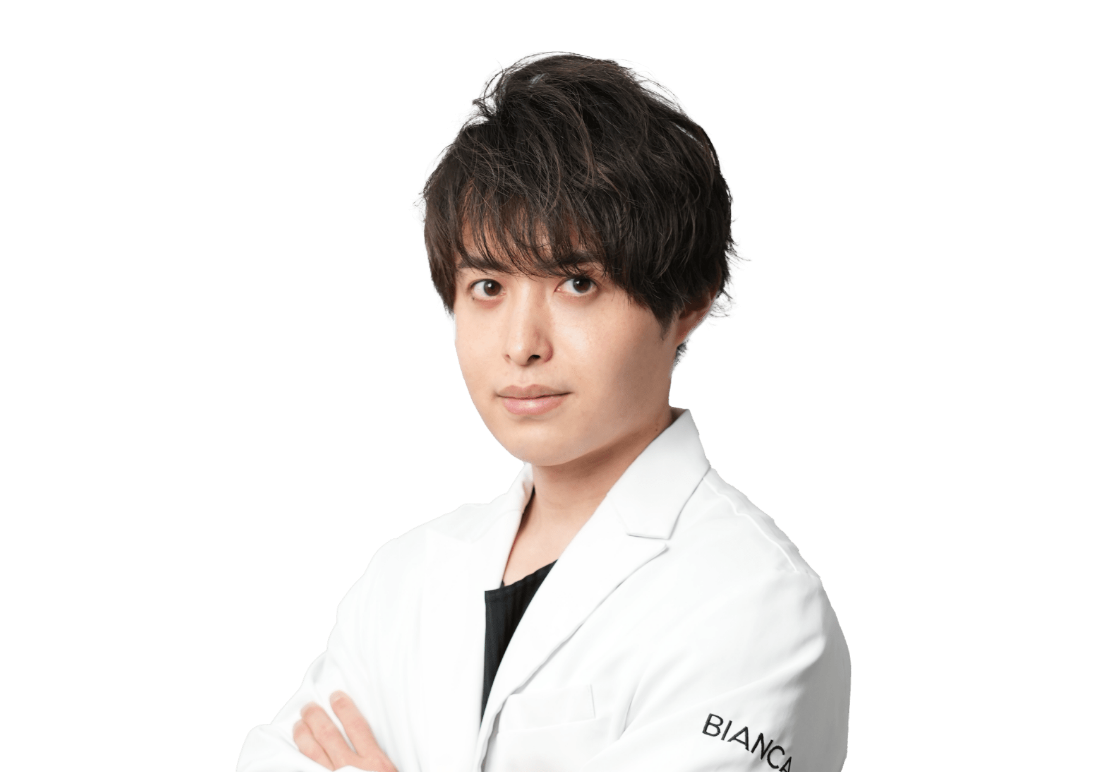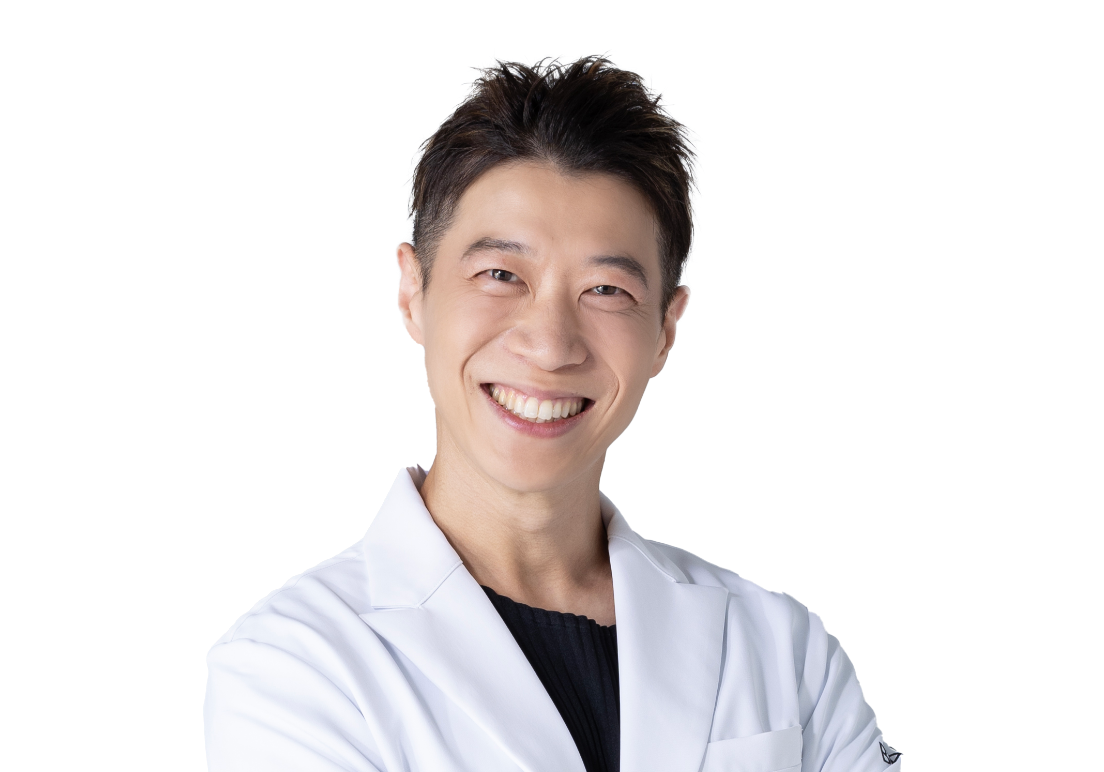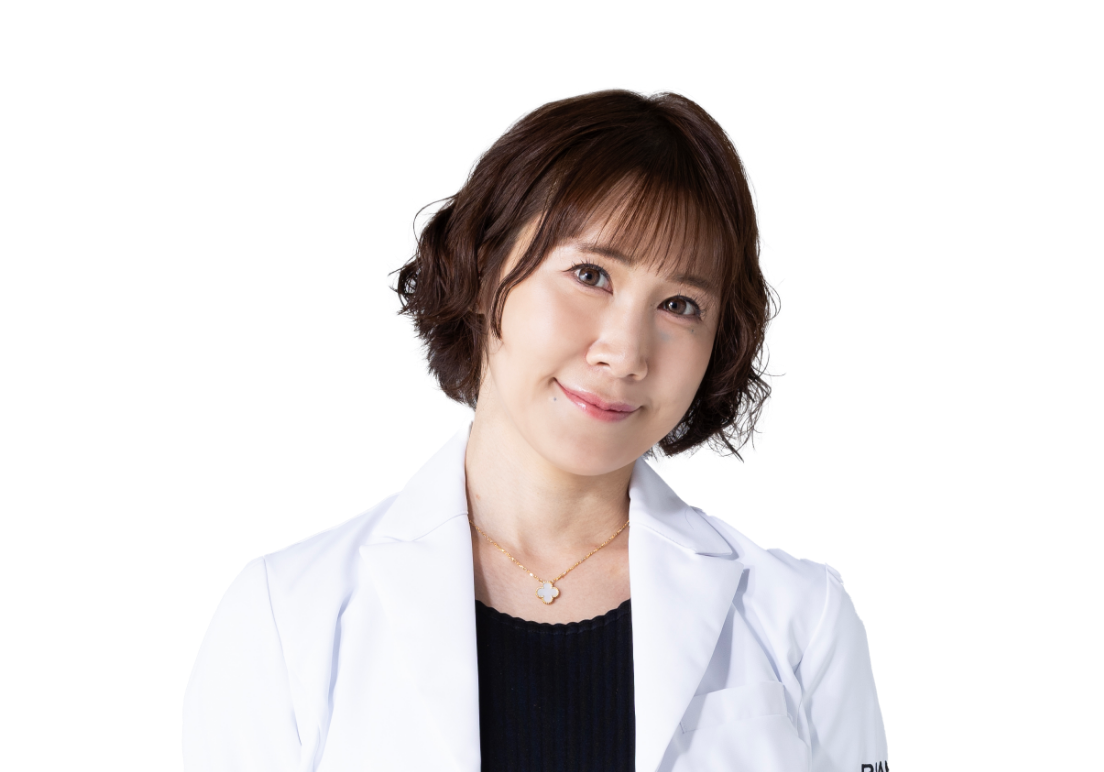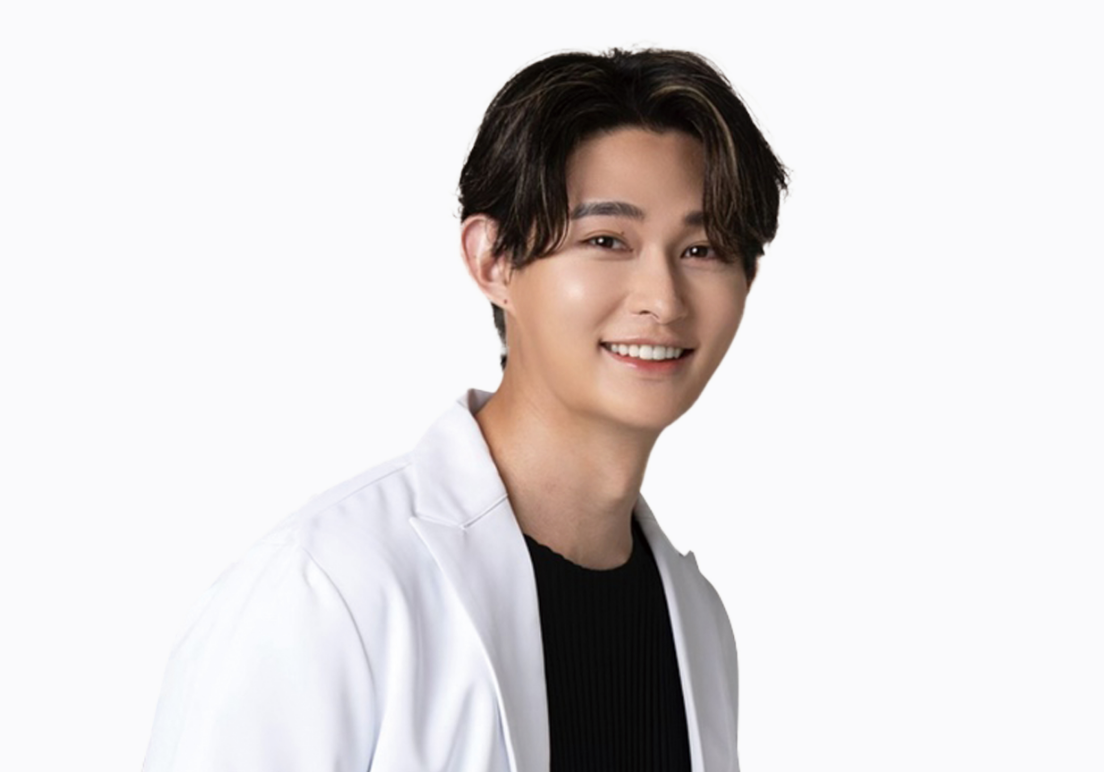コラム
2024.04.03
GLP-1受容体作動薬とは?糖尿病・心血管・神経研究の最前線を美容内科医が解説

美しさを最大限に引き出すには、外側だけでなく内側のケアが欠かせません。海外では一般的なペプチド療法など先進的なエイジングケアを、日本の患者様にも届けたいと考えています。美容内科的アプローチは即効性こそ控えめですが、美と若さを支える土台づくりの要。栄養療法や生活習慣改善に加え、ホルモン補充・ペプチド療法・再生医療を組み合わせ、一人ひとりに適した治療計画を提案。内側からの健康と美しさを長期的にサポートしていきます。
こんにちは。
BIANCA CLINIC(ビアンカクリニック)美容内科指導医の前田陽子です。
今回は、近年医学界でも大きな注目を集めているGLP-1受容体作動薬について、最新の研究や臨床試験の動向をわかりやすくご紹介します。
※本記事は情報提供を目的としており、治療効果を保証するものではありません。
GLP-1受容体作動薬とは?
GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)は、腸から分泌されるホルモンの一種で、食後の血糖コントロールに関わります。
このGLP-1の働きを利用し、薬として応用したものがGLP-1受容体作動薬です。
もともとは糖尿病治療を目的として開発されましたが、血糖値の調整だけでなく、食欲や消化、代謝全般に関与するホルモンとして研究が進められています。
糖尿病発症リスクとGLP-1受容体作動薬の研究
GLP-1受容体作動薬は、血糖管理の改善だけでなく、糖尿病発症リスクにも関連がある可能性が報告されています。
代表的な「SCALE研究」では、肥満を有する対象者をGLP-1群とプラセボ群に分けて比較した結果、GLP-1群で糖尿病の新規発症が少なかったという傾向が報告されています。
ただし、これは治療薬としての使用条件下での結果であり、すべての方に同様の効果があるわけではありません。
心血管・神経疾患領域での臨床研究
GLP-1受容体作動薬は、血糖コントロールを超えて、心血管や神経疾患の領域でも研究が進んでいます。
「SELECT試験」では、GLP-1製剤を使用したグループで主要心血管イベントの発生が減少したという報告があります。
また、動物実験では神経保護作用が示唆されており、アルツハイマー病など神経変性疾患への臨床試験も進行中です。
GLP-1が血糖や代謝を介して神経系にも作用する可能性は、今後の研究でさらに明らかになると考えられています。
新しいGLP-1受容体作動薬と国内の開発動向
現在は、GLP-1と他の薬剤を組み合わせた複合作動薬の開発も進行しています。
臨床段階では代謝改善や体重変化が観察されていますが、安全性と長期的データの検証は今後の課題です。
また、日本の中外製薬が開発中の新しい経口GLP-1受容体作動薬は、食事や水分摂取の制限が少ない仕様が検討されています。
(※開発段階の情報であり、市販や適応は未定です。)
まとめ:GLP-1受容体作動薬の未来
GLP-1受容体作動薬は、糖代謝をはじめ、
-
心血管リスクへの影響
-
神経変性疾患における研究
-
新しい経口・複合タイプの開発
など、幅広い領域で研究が進んでいます。
GLP-1受容体作動薬の可能性がさらに広がることが期待されますね。